今回から、簡単な書評を書いていこうと思います。
今回ご紹介するのは、少し古い書籍ではありますが「絶対にミスをしない人の脳の習慣」という本です。
著者の樺沢紫苑さんは精神科医であり、YOUTUBEでも非常に有名な方です。本書は「なぜ人はミスをしてしまうのか?」を脳科学の視点から解き明かし、誰でもミスを無くせる(減らせる)脳の習慣を教えてくれる一冊となっています。
発達障害の特性を持つ僕にとっては「本当に読んで良かった!」と思える内容でした。本書には数多くのノウハウが紹介されていますが、中でも「これは僕にとって非常に重要だな」と感じた7つのポイントをご紹介します。
是非、皆さんも手に取って読んでみて下さい。絶対に損はしないと断言できるレベルの良著です。
脳は何歳からでも成長できる
著者である樺沢さん自身が、これを証明している所が重要なポイントです。
自分よりも年上の方が、習慣によって脳を成長させている訳です。科学的な根拠だけでなく、自らが実践して結果を出している。これほど心強いエビデンスはありません。
脳は何歳からでも成長し続ける。こう思えるだけでも、色んな事に挑戦しようという気持ちが湧いてきますよね。
本書では脳を鍛える方法も詳細に書かれているので、是非とも実践していきたいと思います。
スマホの使いすぎは「スマホ認知症」を引き起こす
知る人ぞ知る事ではありますが、現代人はスマホに支配されており、スマホによって機能を低下させられています。
実は、この「スマホ認知症」という言葉は僕も聞いた事はありました。しかしながら、当時は鼻で笑っていたのです。「先端機器に理解のない老人が何か言ってるなぁ」くらいの感覚でした。
しかしながら、実際にスマホ漬けの生活を送っていた僕にはもう分かっています。
マジで、スマホは触れば触るほど脳が退化します。YOUTUBEでも「スマホはルーティンの大敵」と言われていますし、触らないに越した事はありません。
本書では、スマホは「1日1時間以下」という目安を科学的根拠に基づいて設けてくれています。便利なアイテムですから、全く使わないのも勿体ないです。上手く付き合っていくべきでしょう。
「3」を意識する事で学びが最大化する
人が一度に覚えられる情報には限界があります。
本書では、人が一度に吸収できる情報(学び)はせいぜい3つくらいと述べられています。それ以上は、詰め込んでも結局は頭に残らないことが多いようです。
これは、身に覚えがあります。授業などで黒板の情報を全てノートに書き写したとしても、ほとんど覚えられませんからね。(あくまでも復習のために写すだけ…復習をしなければ何も残りません!)
最近は読書が習慣になってきているので、試しに1冊の本を読み終えた直後に、本の内容を紙に書き出してみました。結果、物凄くタメになる本だったのに、思い出せた内容は5つくらいでした。
そんなもんなんですよねぇ…人間の記憶ってのは。(苦笑)
それが分かっているならば、いっそのこと「3つだけで良いから覚えよう」という意識を持っておけば良い訳です。10を学ぼうとして1も覚えられないよりは、3つを覚えられる方が遥かに有意義ですからね。
ワーキングメモリも「3」前後が限界
ワーキングメモリとは「脳の一時的な作業スペース」のようなものです。これがキャパオーバーすると、人から受けた命令や、大事な事が頭から抜ける「うっかりミス」が発生します。
本書では、このワーキングメモリを上手く使うための方法に多くのページが割かれており、僕のように、発達特性も相まって「うっかりミス」を連発する人は是非とも読んで欲しい内容です。
ここでも「3」という数字が重要で、やはり人が一時的に覚えられる事など「3つくらい」が精々なのです。
僕がなせ、この数字を「大事だ」と思ったかと言えば…会社員時代、引継ぎの際に矢継ぎ早に口頭でガンガン情報を下ろしてくる人が居て、頑張って全てをメモしたものの、結局は仕事が全く覚えられなかった…という経験があったからです。
今思えば、僕でなくとも無理な引継ぎのやり方だったと思います。仮に僕が同じ事をするならば、事前にレジュメの形で引継ぎ事項を用意して、大事な事を「3つ」だけ教えるでしょう。
「困ったらレジュメを見る」「分からなかったら聞く」「自分でも調べる事も大事」の3つくらいでしょうか。仕事の引継ぎ=膨大な情報を、一度で全て吸収できる訳がないのです。大事な事は、内容よりも「困った時にどうするか」を教える事だと思うんですよね。
話が大きく逸れましたが、皆さんも圧倒的な情報を一度に伝えられそうになったら、こう言うと良いでしょう。
「そんなに沢山の情報を一度に言われても、覚えられません。乱暴にメモを取っても、後で分からなくなりそうです。十分な時間を取ってもらえませんか」と。
さらに「これでも、やってみないと分からないと思います。少しずつ、確実に覚えていくので、何度か聞くと思いますが、よろしくお願いします」と。
これで怒るような相手なら、悪いのは貴方ではなく相手の方です。気に病む必要は一切なし。
僕は昔、これを「自分が出来ないせいだ」と思ってしまいました。早く本書に出会っていれば…と悔やまれます。読書の習慣って、とっても大事なんだな…と感じました。
「できる人のルーティン」は脳に良い
本書で紹介されている「ワーキングメモリを鍛える9つの習慣」のうち、僕は6つをすでに日常的に取り入れていました。
というのも、この6つは「できる人がやっているルーティン」と似たような内容だったからです。
- 規則正しい睡眠を取る(7時間以上)
- 散歩する(やや早足が良い)
- 自然の中で運動する(緑が多い川沿いの散歩でクリア)
- 読書する
- 料理をする(段取り力が身に付く)
- マインドフルネス瞑想をする
ただし、ワーキングメモリを鍛えるという意味ではこれだけでは不十分で、残りの3つは実生活に取り入れられていません。
これについては、本書の内容を細かく書く事が著者の利益と相反する可能性があるため、ここでは伏せておきます。是非、ご自身で本書を手に取って読んでみて欲しいです。(そんなに難しい事ではなく、単に頭を使う何かをする…という程度の事ですが)
とりあえず、僕自身が頑張って取り入れようとしているルーティンに間違いがない事が分かり、今後も頑張って取り組んでいこうと思えました。
TODOは「集中力」を基準に考える事が重要
よくあるタスク管理術では「重要度」「緊急性」が重視されますが、本書では、そこに「集中力が必要かどうか」という視点を付け加える事が大事だと述べられています。
確かに、仕事をしていると「これは集中できる時にやらないと無理だな」と思う内容があります。そういった仕事を夕方頃から着手してしまうと、大体は定時では終わらずに残業になってしまいます。
特に急ぎでない場合でも、集中力を要する仕事で、かつ重要度が高いのであれば、早めに「集中できる時間帯」に終わらせておくべきなのです。逆に、急ぎの仕事であっても、集中力を必要としない場合は夕方頃に着手してもOKということ。
本書には、この考え方に基づいたTODO表の例が記載されています。インターネットでもダウンロード出来るようですが、簡単な表なので自分で作っても良いと思います。
僕の経験上、やや項目数が少ない(事務仕事は細かいタスクが非常に多い)と感じる一方で、1日に出来る仕事量なんて、この程度が限界だよなぁ…と思ったりも。つくづく、僕が辞めた前職の仕事量って半端なかったなぁ…って思い出にふけったりしました。
本書は、人が出来る仕事の目安量をある程度「可視化」する事に成功した本であるとも感じました。
頭の良い精神科医さんが「人間にはこれくらいの事しか出来ないんだよ」という事を、科学的根拠に基づいて書いてくれている。であれば、その枠を超えて仕事をして失敗をしたとして、自分を責める事は無意味であると考える事ができます。
「何もしない時間」が脳にとってメチャクチャ大事
僕もそうですが「1日を通してほとんど何も出来なかった日」って、めっちゃ凹みますよね。
それも、椅子に座ってぼんやりして、うとうとして、つい横になったが最後…気付いたら数時間が経過していた。これはもう、最悪の1日です。日記にも何も書けません。
しかしながら、その「マジで何もしなかった時間」は脳にとって非常に重要な時間だったのです。
著者曰く、何もしていない時でも脳は動いていて、情報を整理しているとの事。
…と言う事は。その時間を設けた事により、脳が疲労から回復したり、次の情報を受け入れる準備が出来た…という事になります。実は「メチャクチャ有意義な時間」だったのです。
そう考えると、スマホで1日中、YOUTUBE・SNS・ニュースサイトなどを見て過ごした場合は…脳がどうなるかは、想像したくもありませんね。翌日に引きずるレベルの脳疲労を蓄える事になります。
「今日は1日、ボーっとできた」というのは、非常に良い時間の使い方です。僕自身、こんな1日を過ごした事はほとんどありません。
今度、意識的にこんな日を作って実験してみようかな…って思いました。
例えば、スマホを持たず、免許と小銭だけ持ってドライブに出かけて、人気のない場所で1時間くらいボーっとする。これで脳が上手く働いてくれるようになるなら、良い時間の使い方ですよね。
まとめ:「ミスを減らしたい人」でなくとも1度は読んだ方が良い
この本を読むと「ミスをした自分を責める」という行為がいかに無意味であるかを思い知らされます。
ミスが起こる原因は、自分の特性や年齢のせいではなく(それも多少はあるかもしれないけど)、脳にとって良くない習慣を知らず知らずの内にやっていたからなんだ…という事が分かるはずです。
日々の習慣を見直す事で、誰もが「ミスをしない(少ない)」人間になれる。そういった希望を持つことの出来る良著でした。
特に、精神科医の先生がエビデンスを元に書いているという点が、自信を持って取り組む原動力にもなると思います。
「自分は、どうしてミスばっかりしてしまうんだろう…」
「集中力が続かなくて、仕事が終わらない…」
そんな悩みを感じている人にこそ、ぜひ手に取ってほしい一冊でした。
.png)
本の内容は一生使えるレベルの事ばかりなので、購入して手元に置いておくべき一冊です。子ども向けにも書いて欲しい…笑
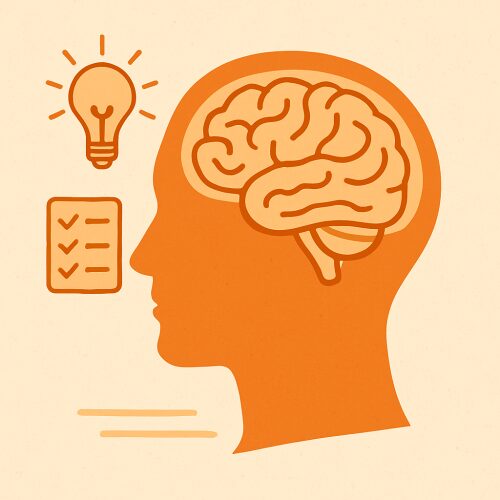
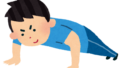

コメント